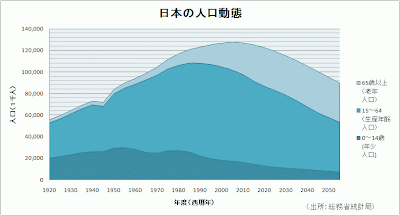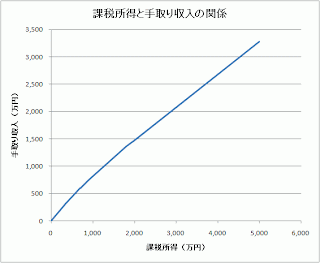医療費タダは良くない
品川区では、子供の医療費はタダである。医者に診てもらっても、薬を処方してもらっても、薬局で薬を受け取っても、文字通り一銭も払わなくて良い。同じように医療費タダの自治体は品川区以外にも多い。子供をもっている親にはありがたい話ではあるのだが、これは今すぐやめたほうが良いと思う。 まず第一に、自治体の財政負担が増加する。医療費タダにできるのは、自治体が肩代わりしているだけである。つまりは、納税者が負担していることなる。患者側に負担意識がないと、ちょっとしたことでもお医者さんに診てもらおうとするので、自治体の医療費負担が増加してしまう。 第二に、医薬業界が焼け太りする。患者側に金銭負担の意識が無いから、医薬業界はなるべく多く医療費を稼ごうとする。そのため、必要以上に多くの薬を処方したり、医療器具をレンタルしようとする。私の子供も、最近たいしたことなさそうなのに、ネブライザーを貸し出してもらった(当然タダ)ものの、結局二回使ったきり使うのをやめてしまった経験がある。 第三に、必要以上に病院が混雑する。負担が無ければ、ちょっと調子が悪いだけでも診てもらおうとなるので、病院が大繁盛となる。そして、本当に診察が必要な子供が待たされる状況が発生する。 では、どうすればいいか。私は、年間の総額で考えて、一定額(一人10万円くらいだろうか)までは医療費は全額自己負担とすればよいと思う。そうすれば、特殊な高額の医療費については自治体が負担されるので、医療費が払えなくて治療が受けられないという事態は避けられる一方で、小額の医療費は負担している意識がはたらくので、必要以上に病院に行かなくなる。 同じ事は、高齢者の医療費負担にも言えると思う。